中国文芸研究会のウェブサイトが次のURLに変更されることになりました。
- 中国文芸研究会新ウェブサイト https://www.c-bungei.jp/wphp/
4月末を目処に、更新情報は新サイトのみに掲載されることになります。なお、本サイトはアーカイブ用サイトとして残されます。
『野草』第109号より、『野草』への原稿投稿専用のメールアドレスを運用することになりました。詳細は以下をご覧下さい。
- 『野草』への原稿投稿について https://www.c-bungei.jp/etc/main.htm#yecao
2022.03.27
会員各位
コロナウイルス蔓延につき、4月の例会も中止とさせていただきます。5月以降についても事態は流動的ですので、随時HPをご確認ください。
なお、総会や会報の扱いについては検討中となっています。事務局で結論が出次第、HPにて発表いたします。
また例会が中止になると、紙媒体の会報の発送が遅れる場合があります。会報メルマガ版も併せてご利用ください。メルマガ版の配信の申込はこちらで承っております。
2020.04.13
|
*三月例会中止のお知らせ (第2報、2020.03.16, 21:55更新) 先立って開催予定と告知した三月例会ですが、コロナウイルスの影響拡大のため、やはり中止せざるをえなくなりました。 |
|
*3月例会につきまして (第1報、2020.03.13, 12:10更新) 新型コロナウイルスが流行しております。会場が閉鎖されない限り三月例会は開催いたしますが、突然状況が変わることもありますので、随時このサイトのチェックをお願いいたします(万が一中止する時はこのHPとMLとでお知らせします)。 当日は『野草』の発送も行いますが、みなさま体調を見てくれぐれも無理なさらないようにしてください。マスク着用、手指の消毒など、各自励行をお願いします。 |
- 〒662-8501 兵庫県西宮市上ヶ原一番町1-155
関西学院大学商学部 藤野研究室気付
中国文芸研究会
「中国現代文学翻訳の歴史と現状」のご案内 2018.10.30
- 日時:2018年11月3日(土)※文化の日 13:30 開場
- 14:00~17:00 懇話会「中国現代文学翻訳の歴史と現状」
(東京大学駒場キャンパス18 号館 コラボレーションルーム1) - 17:30~19:30 懇親会
(同駒場キャンパス18 号館 オープンスペース) - 詳細はこちらをご参照ください。
9月例会会場である関西学院大学大阪梅田キャンパスが、台風接近のために30日の閉館を決定しました。
これにともない、9月例会を休会とさせていただきます。
なお、午前に予定されておりました自伝・回想録を読む会も同様に休会となります。
2018年9月29日17:15 中国文芸研究会事
28日9:00現在、台風12号が関西地方に上陸することが見込まれています。 7月例会会場である関西学院大学大阪梅田キャンパスにおける暴風警報発令時の措置は次の通りです。
**********
関西方面(阪神、播磨南東部、北播丹波、大阪市、北大阪市、東部大阪、南河内、泉州のいずれかの地域、市町村)に「暴風警報」「特別警報」(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)が発令された場合、「授業・試験」と「教室利用 」については、次のとおり取扱いますので、ご注意ください。
- 1. 暴風警報、特別警報の発令時点で臨時閉館とし、「授業・試験」と「教室利用」は中止します。既に開始している「授業・試験」と「教室利用」は、速やかに終了とします。
- 2.暴風警報、特別警報が解除された場合、解除時刻によって、開館時間が異なります。詳細は、下記URL、もしくは添付ファイルをご覧ください。
https://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/pdf/OUCtyphoon20151019.pdf
**********
中国文芸研究会事務局ではこれにもとづいて9月例会開催の可否を決定します。
開催についての情報はウェブサイトで随時お知らせいたします。
2018年9月28日19:30 中国文芸研究会事務局
28日9:00現在、台風12号が関西地方に上陸することが見込まれています。 7月例会会場である関西学院大学大阪梅田キャンパスにおける暴風警報発令時の措置は次の通りです。
**********
関西方面(阪神、播磨南東部、北播丹波、大阪市、北大阪市、東部大阪、南河内、泉州のいずれかの地域、市町村)に「暴風警報」「特別警報」(大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪)が発令された場合、「授業・試験」と「教室利用 」については、次のとおり取扱いますので、ご注意ください。
- 1. 暴風警報、特別警報の発令時点で臨時閉館とし、「授業・試験」と「教室利用」は中止します。既に開始している「授業・試験」と「教室利用」は、速やかに終了とします。
- 2.暴風警報、特別警報が解除された場合、解除時刻によって、開館時間が異なります。詳細は、下記URL、もしくは添付ファイルをご覧ください。
https://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/pdf/OUCtyphoon20151019.pdf
**********
中国文芸研究会事務局ではこれにもとづいて7月例会開催の可否を決定します。
開催についての情報はウェブサイトで随時お知らせいたします。
2018年7月28日 中国文芸研究会事務局
【続報】7月例会の開催について
本日29日午前8時までに兵庫・大阪の暴風警報が解除されたので、7月例会は予定通り開催いたします。
なお、午前に予定されていた「自伝・回想録を読む会」は延期となりました。
会報5月号に掲載した2017年度の総会議案書を、次のように訂正します。
会報5月号総会議案書・2017年度活動方針の訂正
〔誤〕第100号記念号=2017年9月末原稿提出〆切、2017年12月刊行。編集:100号記念号編集委員会
〔正〕第100号記念号=2016年9月末原稿提出〆切、2018年3月刊行。編集:100号記念号編集委員会
2017年度中国文芸研究会総会(2017年4月30日開催)において、英語による研究会名の表記が決定しました。
中国文芸研究会の英語表記 = Japanese Association for Chinese Literature and Art Studies (JACLAS)
英語による業績書などをご作成の際にご参照ください。
- 日時:2017年2月19日(日)12:30~17:30
- 場所:関西学院大学 大阪梅田キャンパス 1402号室
2月は例会がありませんので、『野草』第99号の最終校正を上記日程で行います。 お忙しい時期とは思いますが、当日は少しでも多くの皆様のご協力をお願いいたします。 短時間のご参加でも問題ありません。 どうぞよろしくお願いします。
2018年2月、『野草』は100号を迎えます。1970年の創刊以来、民間の一研究団体が専門的な研究誌を40余年にわたって維持、発展させてきたことは、日本の学術界でも稀有のことであり、『野草』を護り育ててこられた先輩の方々のご努力には、敬意の念を禁じ得ません。また、こうした伝統を受け継いでゆくことにも大きな喜びを感じております。
しかし、近年、『野草』の母体である中国文芸研究会の会員数は伸びず、事務局員や例会参加者の世代交代も順調に進んでいるとは言えません。わたしたちは、この機に『野草』100号編集委員会を立ち上げ、こうした現状を打開するには何をすれば良いのか、『野草』が魅力ある研究誌であり続け、中国文芸研究会が活気に満ちた研究団体であり続けるためには、何が必要かを繰り返し議論しました。
その結果たどり着いたのは、会員の中に潜む未知の可能性を掬いあげ、それを研究会の総力を挙げて形あるものに仕上げることにより、研究会が総体として、自らを新しい水準に引き上げてゆくということでした。研究誌、研究会が、最後にその将来を託すことができるのは、会員しかありません。このようにして形あるものとなった論文を掲載する場として、『野草』100号記念号を企画したいと思います。『野草』100号記念号は、通常の号とは異なり、単行本として独自の書名をつけ、出版社に依頼して刊行する予定です。
このような考えのもとに、『野草』100号編集委員会は、現在までに何度かの編集会議を開き、既に主として若い世代の会員を対象とし、100号記念号への投稿を慫慂するなどの編集準備を進めております。
こうした編集準備の締めくくりとして、この度、会員の皆様に対し『野草』100号記念号への原稿募集を行う運びとなりました。投稿を希望される方は、以下の投稿要領をご覧の上、11月3日(火)までに、執筆予定論文のタイトルおよび構想(800字程度)を、編集委員会までお寄せ下さい。
よろしくお願い申し上げます。
9月吉日 『野草』100号編集委員会一同
(委員長)北岡正子
青野繁治、今泉秀人、宇野木洋、大東和重、城山拓也
濱田麻矢、藤野真子、松浦恆雄、三須祐介
*『野草』100号記念号投稿要領
- 枚数:50枚程度。
- テーマ:自由。ただし、文学史や時代精神を意識した論の展開にご留意下さい。
- 締め切り:2016年9月30日。
- 査読:あり(査読によって改稿を求める場合があります。再査読の結果、掲載を見送る ことがあります)。
- 執筆者負担:専任は三冊買い取り(約15000円程度)、それ以外は一冊買い取り(約5000円程度)
*論文タイトルおよび構想(11月3日(火)締め切り)
- 構想は800字程度。
中国文芸研究会の代表をつとめておられた太田進先生(同志社大学名誉教授)が去る11月12日に逝去されました。先生は1970年の会の創立以来、四十年もの間研究会の中心となって活躍してこられました。 ここに謹んで哀悼の意を表するとともに、心から先生のご冥福をお祈りいたします。
2012.11.28
- 09.30掲載
- 9月30日に開催予定だった9月例会(『野草』第90号)及び黄錦樹先生の「お話し」は、台風接近に伴う暴風警報発令により会場が使用できなくなったため、やむなく中止とさせていただきます。参加を予定されていた皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、どうかご了承ください。今後の詳細は追ってこのウェブサイトでお知らせいたします。
- 10.13掲載
- 9月例会(『野草』第90号合評会)は延期されました。今後の詳細は追ってこのウェブサイトでお知らせいたします。
- 9月例会当日に発送予定だった紙版の会報第371号は10月末に次号と同時発送となります。
- 10.29掲載
- 9月例会(『野草』第90号合評会)は、12月例会で行われることになりました。日程等の詳細は11月末発送の会報、及びこのウェブサイトで追ってお知らせいたします。
- 会場
- 神戸大学百年記念館
- 主催
- 科研費基盤研究(B)「漂泊する叙事 1940年代中華圏における文化接触史」/台湾‧財団法人自由思想学術基金会/神戸大学
- 共催
- 東京台北文化センター
- 使用言語
- 日本語、中国語(通訳なし)
- *来聴歓迎 参加費無料
------------------------------------
- 11月10日(土)
- 基調講演 10:00〜10:40
- 廖炳惠(カリフォルニア大学サンディアゴ校)
- 戦争と女性:蕭紅、張愛玲、齊邦媛、龍応台たちの作品における幸福と不幸、傷跡と記憶
- 池上貞子(跡見学園女子大学)
- 戦争と女性―齊邦媛『巨流河』・林白『たったひとりの戦争』翻訳所感
- 基調講演 10:00〜10:40
- セッション1「テクスト・記憶・性別」10:50〜12:20
- 司会:津守陽(神戸市外国語大学)
- 報告1劉鋒杰(蘇州大学)
- 張愛玲『燼余録』と戦争文化心理
- 報告2 今泉秀人(大阪大学)
- 沈従文作品における戦争と女性のイメージ―「夢と現実」、「摘星録」、「看虹録」をめぐって
- 報告3 濱田麻矢(神戸大学)
- 一九四九年の語り方——−龍應台『大江大海 一九四九』
- 司会:津守陽(神戸市外国語大学)
- セッション2 「流通する女性像」13:30〜15:50
- 司会 田村容子(福井大学)
- 報告1 賀桂梅(北京大学)
- 戦後六十年の日中映画における敗戦の記憶と女性表現
- 報告2 西村正男(関西学院大学)
- 混淆・越境・オリエンタリズム——「玫瑰玫瑰我愛你」(Rose, Rose, I Love You)の原曲とカヴァー・ヴァージョンをめぐって
- (茶叙)
- 報告3 張小虹(台湾大学)
- インダンスリン・ブルー ——分子戦争と分子女性
- 報告4 梅家玲(台湾大学)
- 婦女手中の線、将士身上の衣——五〇年代台湾婦聯会の「征衣」における女性/身体と空間政治
- 司会 田村容子(福井大学)
- 11月11日(日)
- セッション3 「『巨流河』とその時代」10:00〜12:20
- 司会 単徳興(中央研究院)
- 報告1 神谷まり子(国士舘大学)
- 『巨流河』——歴史・自伝・女性
- 報告2 張学昕(遼寧師範大學)
- 時間の上:“ノンフィクション”の歴史と人生——齊邦媛『巨流河』と“ノンフィクション”創作
- (茶叙)
- 報告3 杉村安幾子(金沢大学)
- 金沢第四高等学校時代における齊世英
- 報告4 薛化元(政治大学)
- 外省人自由派エリートと戦後台湾における政治改革への訴求——齊世英を中心に
- 司会 単徳興(中央研究院)
- セッション3 「『巨流河』とその時代」10:00〜12:20
- セッション4 「植民地とジェンダー」13:30〜15:00
- 司会:盧非易(政治大学)
- 報告1 星名宏修(一橋大学)
- 看護助手、海を渡る——河野慶彦「湯わかし」を読む
- 報告2 劉霊均(中国文化大学)
- 軍艦の性別——安西冬衛の戦前詩における「女」軍艦と「男」性叙事者
- 報告3 陳儒修(政治大学)
- 戦争における女性と「大きな物語」の崩壊
- 司会:盧非易(政治大学)
- 総合討論 15:20〜16:00
- 廖炳惠 単徳興 濱田麻矢 賀桂梅 劉鋒杰
清秋の候、皆様方にはご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、本年度の中国現代文学研究者懇話会は、例年通り、日本中国学会(於大阪市立大学)の前日、10月5日(金)に開催いたします。
今回は、国立暨南国際大学中文系教授・黄錦樹さんをお招きして、馬華文学における自らの位置についてご講演いただくことにいたしました。黄錦樹さんは、馬華文学を代表する作家・評論家であると同時に、中国現代文学の研究者としても優れた仕事をしておられます。昨年、日本で小説集『夢と豚と黎明――黄錦樹作品集』(人文書院、2011年)が出版されました。このたび縁あって、黄錦樹さんを大阪にご招待することができました。連絡役になっていただいた黄英哲さんには、この場を借りて篤くお礼申し上げます。
10月初旬のお忙しい時期かと存じますが、めったにない機会かと存じます。万障お繰り合わせの上、ご臨席賜りますようお願い申し上げます。
中国現代文学研究者懇話会 準備会
北岡正子・青野繁治・宇野木洋・松浦恆雄
2012年9月11日
記
- 第一部 懇話会
- 日時:2012年10月5日(金)14:30~17:30
- 開場:14:00
- 会場:大阪市立大学文化交流センター・ホール(大阪駅前第二ビル6階)
- 会費:1000円
- 講演:黄錦樹「在馬華文学的隠没帯」
与談者:濱田麻矢、大東和重、羽田朝子、橋本恭子 - 開場:14:00
- 第二部 懇親会
- 日時:2012年10月5日(金)18:00~20:30
- 開場:17:45
- 会場:King of Kings(大阪駅前第一ビルB1階)
- 会費:5000円(院生3000円)
- 開場:17:45
出欠は、案内状に同封いたしました返信用葉書に必要事項をご記入の上、9月21日必着でお知らせ下さい。また、下記のメールアドレスでも出欠のご連絡を受け付けます。 「gendaikonwakai※gmail.com(※を@に置き換えてください。)」ご住所、ご氏名、ご所属を明記の上、9月21日までにお知らせ下さい。 もちろん案内状が届いていない方の参加も歓迎いたします。
なお、中国文芸研究会でも、9月例会の開始前に黄錦樹さんにお話をして頂くことを予定しています。会員の皆様のご参加をお待ちしています。
- 日時:2012年9月30日(日)10:30~12:30
- 会場: 関西学院大学梅田キャンパス 1005号室
- お話:黄錦樹「論胡蘭成的神話學」
- 会場: 関西学院大学梅田キャンパス 1005号室
- 10月28日 於・関西学院会館 翼の間
- 12:40-13:30
- 『生命―希望の贈り物』と『跳舞時代』の一部を上映
- 13:30-15:00
- 邱貴芬氏(国立中興大学教授)講演「台湾ドキュメンタリ映画と台湾社会運動」(討論者 林怡蓉(関西学院大学))
- 15:10-16:40
- 呉乙峰氏(映画監督、『生命―希望の贈り物』他)講演(討論者 濱田麻矢(神戸大学))
- 16:50-18:20
- 簡偉斯氏、郭珍弟氏(『跳舞時代』他)講演(討論者 西村正男(関西学院大学))
- 総合討論
- 主催 中国文芸研究会
- 共催 台湾・自由思想学術基金会
- 後援 行政院文化建設委員会(Council for Cultural Affairs, R.O.C.Taiwan)
- 司会 朱恵足(台湾・中興大学)・濱田麻矢・西村正男
- 通訳 朱恵足・小笠原淳(神戸大学大学院)・村島健司(関西学院大学大学院、台湾・慈済大学大学院)
| 会報7月号発送のご協力のお願い 2010.07.25 7月の会報発送作業は、以下の日程で行います。どうかよろしくご協力ください。
|
『野草』86号の最終校正を以下の通り行います。ご協力いただける会員は是非ご参加ください。
- 日時:7月11日(日) 14:00-17:30
- 関西学院大学 梅田キャンパス1405号室 会場案内
2008年度 中国現代文学研究者懇話会の御案内 2008.09.08、訂正09.26
恒例の中国現代文学研究者懇話会(通称前夜祭)を下記の通り開催します。毎年御案内しております各位には別便にて御連絡いたしましたが、案内洩れがあるやも知れませんので、この場を借りて御案内いたします。多数の皆様の御参加をお待ち申し上げております。
2008年度 中国現代文学研究者懇話会の御案内
立秋よりはやひと月、すでに虫の声が涼やかに響く時節となりました。皆様方には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、本年度の中国現代文学研究者懇話会(通称 前夜祭)は、京都大学で開かれる日本中国学会の日程にあわせ、従来通りその「前夜祭」として、10月10日に、立命館大学衣笠キャンパスにて開催いたします。
関西の世話人が集って、以下のようなプログラムを編んでみました。まず、京都開催の地の利を生かし、普段はあまりお話を拝聴する機会のない平田昌司先生(京都大学)をゲストとしてお招きしました。
次に、この会の発起人の一人である丸尾常喜先生の急逝を心から悼み、先生の人と学問を記念してお話いただく場を設けました。
いずれの企画も、フロアの皆様とも活発に交流することができればと考えております。
10月初旬のお忙しい時期とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご臨席くだされば幸甚です。
中国現代文学研究者懇話会 準備会
世話人会(関西) 松浦恆雄
2008年 9月
記
- 第一部 懇話会(討論と記念)
- 日時:2008年10月10日(金)16:00―18:40
- 開場:15 : 30
- 会場:立命館大学衣笠キャンパス恒心館730教室
- 会費:1000円
- 討論:(テーマ)目の文学革命・耳の文学革命
- ゲスト:平田昌司(京都大学)
- 討論者:西村正男、松浦恆雄
- 記念:丸尾常喜先生 人と学問
- 発言者:渡邊晴夫、永井英美、鈴木将久
- 開場:15 : 30
- 第二部 懇親会
- 日時:2008年10月10日(金)19:00―20:30
- 開場:18 : 30
- 会場:末川記念会館地下レストラン「カルム」
- 会費:3000円
- 開場:18 : 30
- 【第一部(討論)参考文献】
- 平田昌司「目の文学革命・耳の文学革命―一九二〇年代中国における聴覚メディアと「国語」の実験―」(『中国文学報』第58册、 1999年)
- 平田昌司「しゃべる女・叱る男―中国の話し言葉にみられるジェンダー規制」(『興膳教授退官記念中国文学論集』汲古書院、2000 年)
- 平田昌司「恋する陳寅恪―中国近代学術にとっての“異性”」(『西洋近代文明と中華世界』京都大学出版会、2001年)
- 平田昌司「しゃべるな 危険―17-20世紀中国の女のことば」(『漢字圏の近代』東京大学出版会、2005年)
- 平田昌司「胡適とヴィクトリアン・アメリカ」(『東方学』第115輯、2008年)
恐縮ながら、はじめて御出席を希望なさる方は、葉書に、住所、氏名、所属、「懇話会」「懇親会」の別を御記入の上、9月17日まで、下記宛にお知らせ下さい。
宛先:〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 大阪市立大学文学部 松浦恆雄
研究会サイトとメールアドレスの変更について 2008.05.10
このたび、研究会ウェブサイトをレンタルサーバーで運用することになりました。
これにより、研究会サイトのURLが次のように変更されました。
| 研究会新ウェブサイトURL: http://c-bungei.jp/bungei.shtml |
また、事務局メールアドレスも、次のように変更されました。
事務局新メールアドレス: 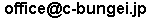 |
下記の連絡については、今後は新メールアドレス「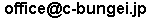 」宛へお願いいたします。
」宛へお願いいたします。
会員のみなさまにはご理解・ご協力くださいますよう、お願いいたします
詳細については、会報5月号に掲載予定の「2008年度総会議案」をご覧ください(議案は、ウェブサイトにも反映されます)。
なお、旧ウェブサイト・旧メールアドレスともに当面の間は利用できますが、徐々に新ウェブサイト・新メールアドレスへ切り替えていきますので、ご留意ください。
研究会メールアドレスの復活について 2008.04.25
「研究会メールアドレス停止のお知らせ」(2008年3月26日)で、使用停止をお知らせしました旧メールアドレス が復活いたしました。
が復活いたしました。
これにより、「新しい研究会メールアドレスのお知らせ」(2008年3月31日)でお知らせしたメールアドレス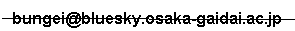 が使用停止となりましたので、ご注意ください。
が使用停止となりましたので、ご注意ください。
これに伴い、次の各項目の連絡も従来通りのメールアドレス 宛にお願いいたします。
宛にお願いいたします。
なお、『中国文芸研究会会報』第318号(2008年4月末発送予定)に掲載されましたメールアドレスのお知らせは、原稿締切の関係上、今回のメールアドレス復活の情報は反映しておりません。この点につきまして、どうぞご了承ください。